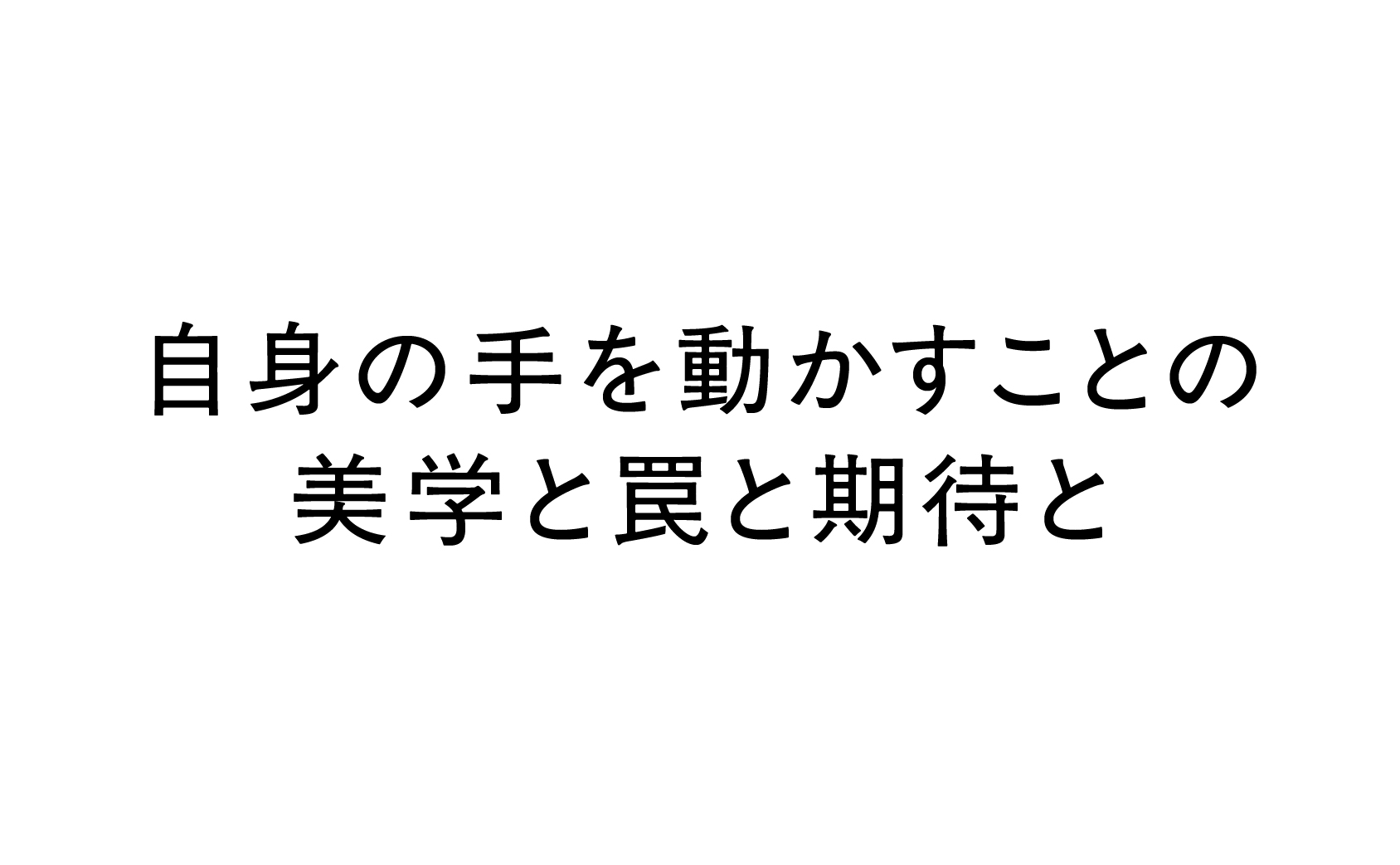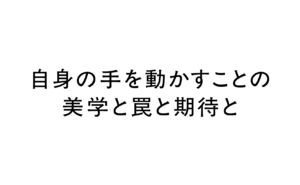うんざりしている。
「AIを活用しないデザイナーは遅れている」や、ポテトTips(皮肉)に。
ぼく自身SNSが好きだから仕方ないのだろうけど目に入りすぎる。
いつからタイムラインに汚染物質が入り込むようになったのだろう。こうあって欲しいと願うSNSはもう……。
そんな雑なところから、ふと記事タイトルの「自身の手を動かすことの美学と罠と期待と」を考えてみる。
他のデザイナーさんと同じように、ぼくの中にも健全かどうかはわからないけれど「デザイナー」としての心がある。それはデザイナーというよりかは「クラフトマン」としての心に近いかもしれない。
デザイナーは手を動かすべき、そう思っているし信じていたい。だけどそう悠長にしてはいられないのがAIの登場である。
今まではAIには出来ないコンセプトメイクやデザインをやってきたつもりだ。ChatGPTが登場してからも、向こう5年は今までのやり方でやっていけるだろう、とタカを括っていた。でもどうやらAIというものは進化がとてつもなく早いらしい。それもそうか、自身の成長曲線と一緒にしてはいけないよな。
“クラフトマンシップのある”デザイナーは自身の手を動かしたがる性分、だと思っている。綺麗な丸をフリーハンドで描けることはとても素晴らしい技術だと思う反面、その技術を認めてくれる、ないしは、そこに価値を見出してくれる世の中ではないことはもう遙か何十年も前から誰もがわかっていることだと思う。
だがしかし、そこにロマンを感じてしまう気持ちもわからなくもない。この狭間が罠、ではないだろうか。二分化されることを自ら選び取っている、そのことを棚に上げていることさえある。
コンパスがあれば綺麗な丸は描ける、むしろ短時間で複製・量産が可能だ。そしてそれはPCを使えばさらに寸分違わずに複製ができる。それでも、フリーハンドで描かれた丸にロマンを感じる人はいる。かくいうぼくも、その一人だ。
人間が手を動かして生み出すものには、必ずと言っていいほど“ゆらぎ”がある。デジタルの精密さではなく、手のわずかな震えや、力の入り具合による微妙な線の揺れ。こうした不完全さが生み出す美しさが、人間的なぬくもりを感じさせる。クラフトマンとしてのデザイナーは、そうした“ゆらぎ”に価値を見出してしまうのだ。
だが、時代はそれを求めているのか?
AIによるデザインは圧倒的なスピードで進化している。パラメトリックデザインやジェネラティブアートといった分野では、もはや人間の手を介さずとも、美しく整ったデザインが瞬時に生成される。過去のデータを参照し、膨大な選択肢の中から最適解を導き出すAIは、労働時間やパワハラ・モラハラ、そのほかにも様々なネガティブなことをこちらに都合よく無視してくれる、口には出せなかった本当に欲しかった(自分よりも)優秀なアシスタントデザイナーなのかもしれない。
手を動かすことにこだわるデザイナーは、果たしてそれに太刀打ちできるのだろうか?
それでも、ぼくは手を動かし続けたいと思う。デザインとは単なるアウトプットではなく、プロセスそのものが価値を持つからだ。手を動かしながら考え、試行錯誤し、偶然の発見に出会う。AIが提案する最適解にはない“偶発性”こそが、デザインを生業としているデザイナーの喜びのひとつでもあるからだ。
とはいえ、AIを拒絶してばかりもいられない。
デザインの仕事は今後ますます変化していくだろう。AIが生み出すデザインの質が向上すれば、クライアントは「人間のデザイナーに頼む意味」を考え始める。では、私たちはどこに活路を見出すべきか。
AIが描くデザインの「正しさ」は、ある意味で機械的な正しさでしかない。それを“意味のあるデザイン”すなわち“記号”に昇華させるのは、やはり解釈項としての人間、つまり解釈の力だ。
では、「罠」とは何か。
AIに頼らずに手を動かすことにこだわるあまり、時代の流れから取り残されること。それも一つの罠だろう。しかし、それ以上に怖いのは「AIを使いこなすことでデザインの本質を見失う」ことではないだろうか。
AIが生成するデザインをそのまま受け入れ、それを微調整するだけの存在になってしまうこと。思考せず、解釈せず、ただアウトプットを流用するだけになってしまうこと。デザイナーの仕事が単なる“オペレーション”になってしまう危険性は、決して小さくない。
AIを使うこと自体が悪いわけではない。むしろ、積極的に活用するべきだ。問題は、それに依存しすぎることによって、デザインの本質的な価値を見失うことなのだと。
そして、「期待」について。
ぼくはAIと共存するデザイナーの未来に、決して悲観的ではない。むしろ、AIがあるからこそ、ぼくらの手が生み出す価値がより際立つ時代になるのではないかとも思うし思いたい。結局のところ、AIの登場によってデザイナーの価値が問われているのは確かだ。しかし、それは「デザインとは何か?」を再定義するチャンスでもある。
そして今一度考え直したいのはAIが瞬間で出来ることを人にやってもらうと、これでもかというほどに時間を要するということ。世の中の価値観や倫理観を破壊していることをもっと危機感を持ち合わせていたい。AIは簡単に人をバカにする。バカにするというのは、自身のことをバカにするということと、他人をバカにするということの、内と外どちらとものことを指している。
「期待」という言葉は責任をこちら側で持つときに使うのと、時の流れに身を任せて使うのとでは雲泥の差がある。ぼくはAIにどちらの期待をしているのだろうか、それは未だによくわからない。考えたくないのと、考えてもAI自体の進化が早い分、自分が答えを出すよりももっと早くにネタバレされてしまう可能性がすこぶる高いことを考えると楽しくないからだろうか。
手を動かすことの美学は、これからも変わらないだろう。ただ、それをどう活かすかは、自分たちの選択にかかっている。そして、デザイナーがこの問いにどう向き合うかによって、「デザイナーの未来」は大きく変わるのかもしれない。
「デザインとは関係性である」とポール・ランドは言った。ぼくがとても大切にしている言葉の一つでもある。
ここに自身の現段階での考えも列挙してみたい。
デザインとは「翻訳」ではないだろうか、と思っている。
何か(A)と何か(B)を繋ぐための言語を、それぞれの環境や文化、様式、構造にチューニングして受け渡しをする、そのような行為を「翻訳」だと捉えている。なのでデザイナーは言うなれば音声だけではない、原義というべきか広義というべきかの言語の「翻訳家」のようなお仕事をしているのだろうと思っている。
そもそもUIとUXを考えていないデザインってあるのだろうか?ないよね?
本を忘れた暇な電車移動の中で書いたので草稿のような稚拙な文章、構造でごめんなさい。次で降りるので逃げるように終わります。特に何が言いたかったかわからないまま終わってしまった。AIに後半書いてもらうか?つまらないだろうか。逃げられるのも人間だからかな。便利だな人間。